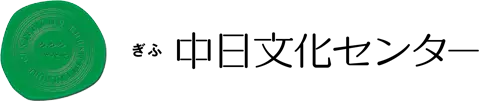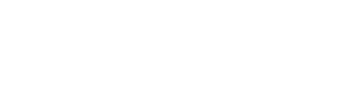7月からの新講座
初めてのピラティス
~お腹のスイッチを入れるための3回シリーズ
姿勢改善専門スタジオアルコス Ako
第2水曜10時50分~正午
3カ月(3回)分 9,240円(税込み)

ピラティスはドイツ出身で米国に移住したフィジカルトレーナー。第1次世界大戦中に負傷兵のリハビリテーションに取り組み、1920年代に身体機能を改善する独自のエクササイズ方法を確立した。最初はニューヨークのダンサーたちに広まり、現在は欧米やアジアなど世界中で行われている。
シンプルで負荷も高くないため、だれでも安心して始められる。「なんだか肩や腰の調子が悪い」「最近、疲れやすくて」という心配がある人、「将来のために健康な身体づくりをしたい」という人たちも最適だ。
レッスンは呼吸法の習得から始め、呼吸に合わせて仰向けや横向きなどさまざまな姿勢で身体を動かしていく。基礎的な体の使い方や動かし方を学びながら、けがを防ぐ。
さらにピラティスが重視するのは「体幹(インナーマッスル)」。腹筋や骨盤の筋肉を正しく使う方法に焦点を当て、呼吸との連携を通じてこれらの筋肉を効率的に活用する。
3回の講座では、エクササイズを厳選し、同じ動作を繰り返す。これによって体の正しい使い方を習得し、しなやかな身体づくりを目指す。