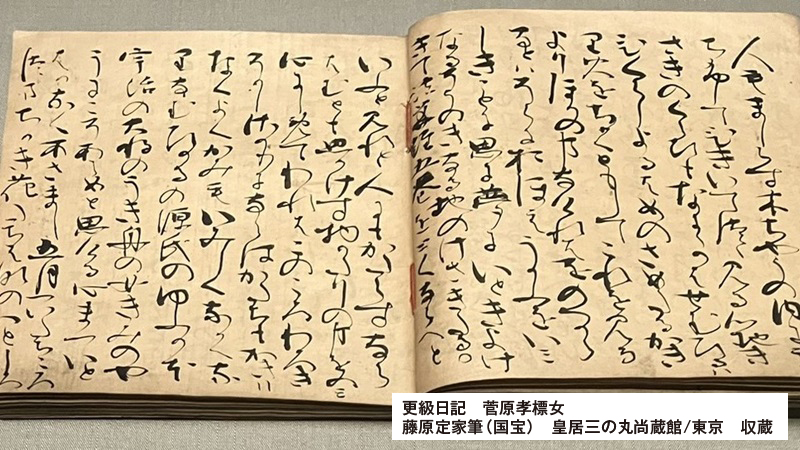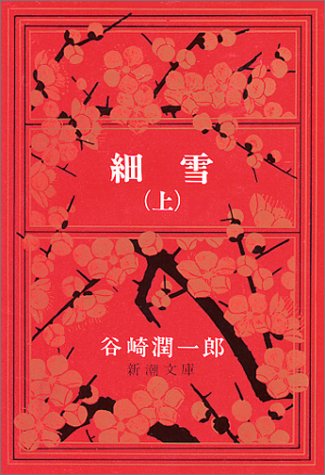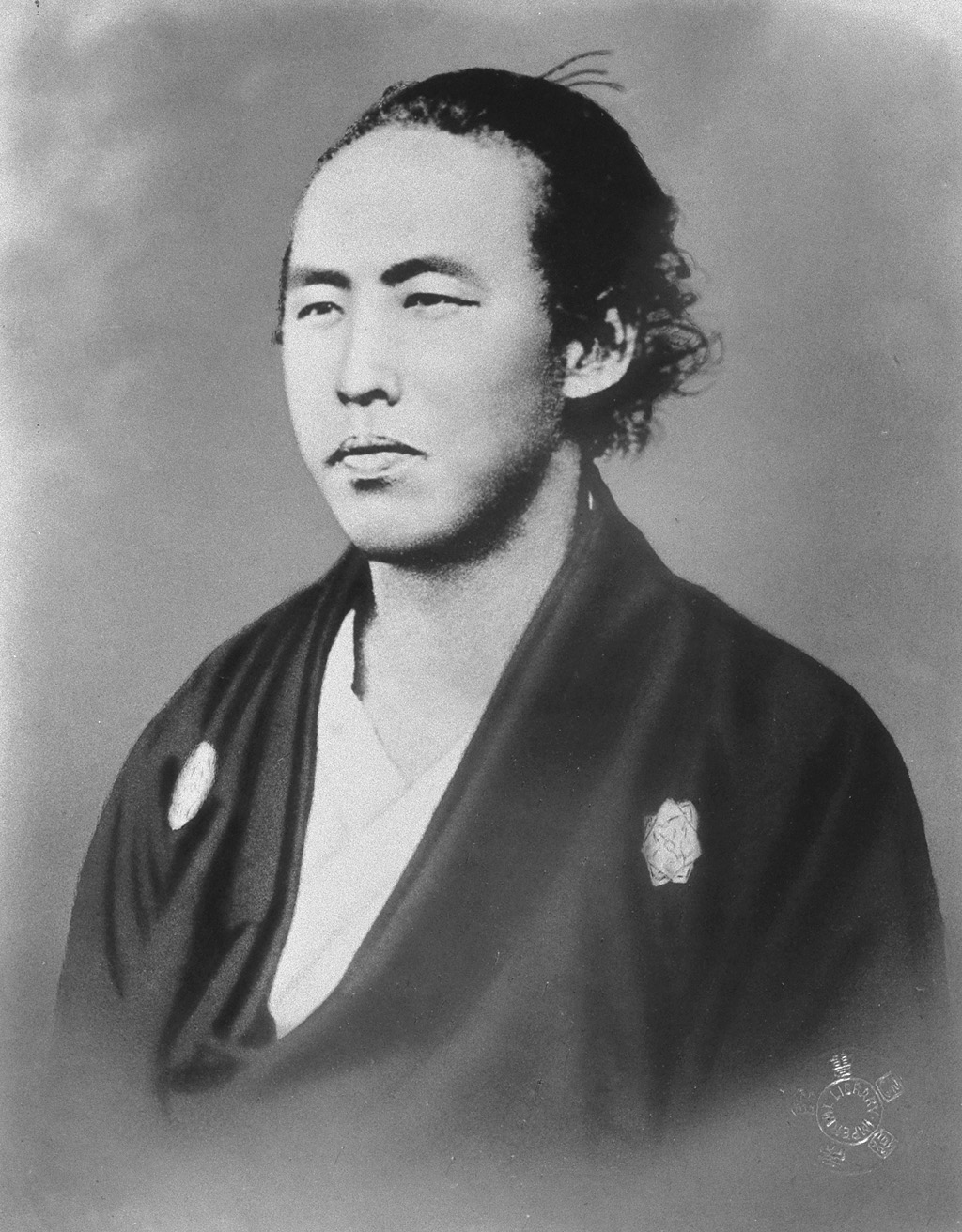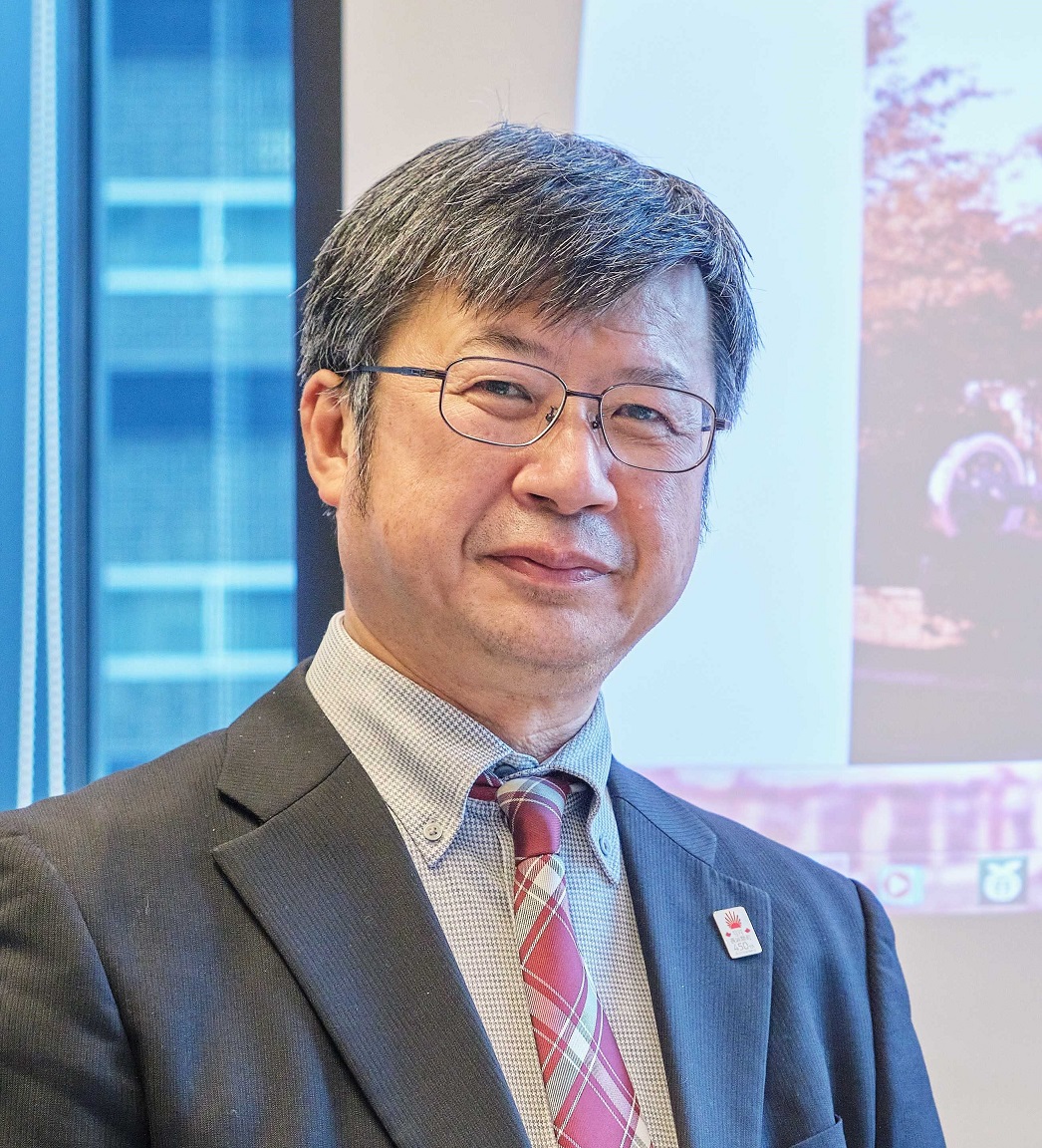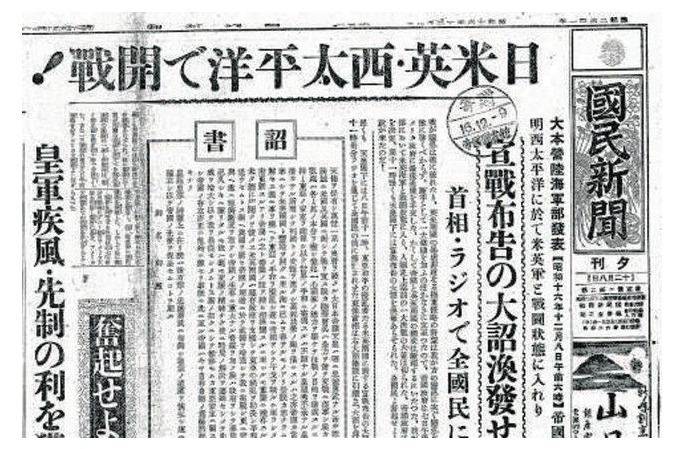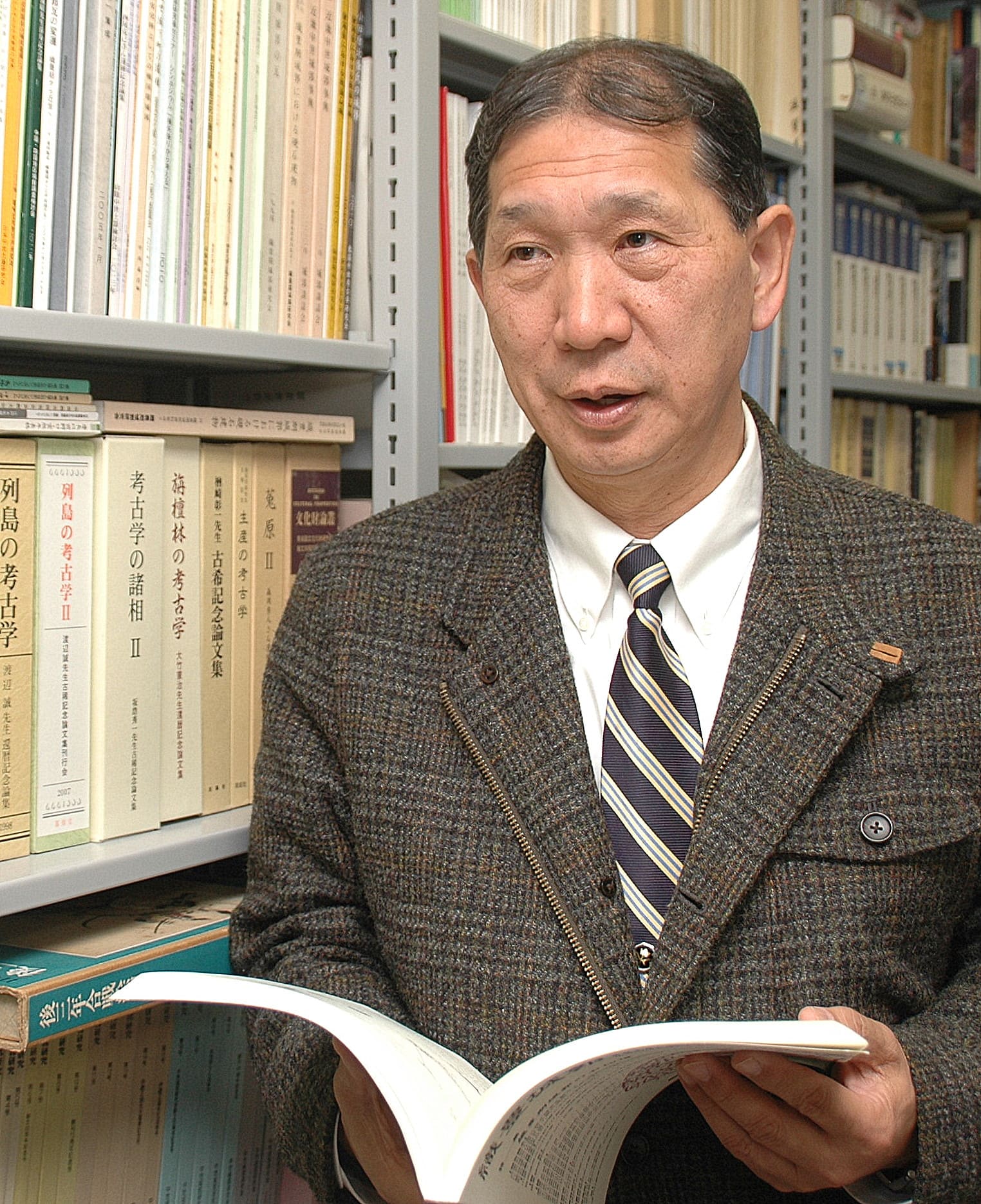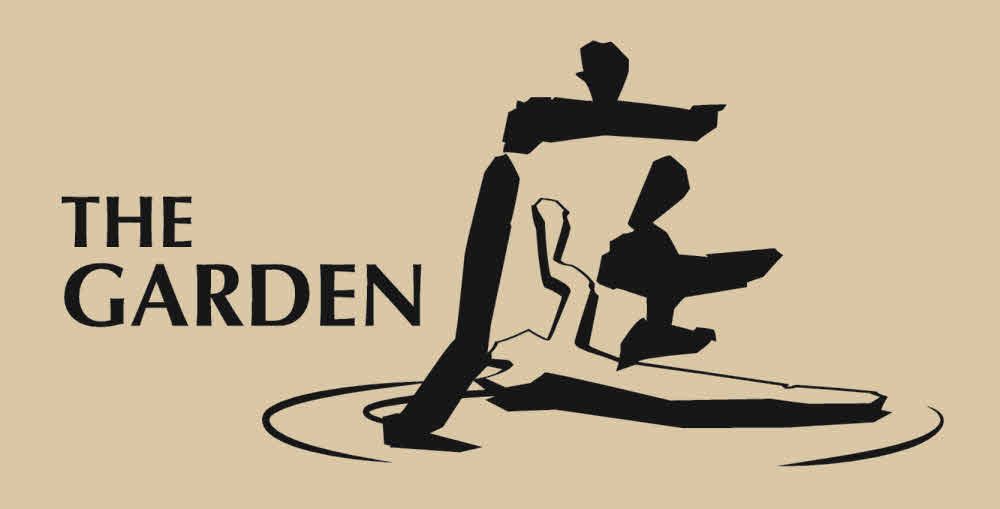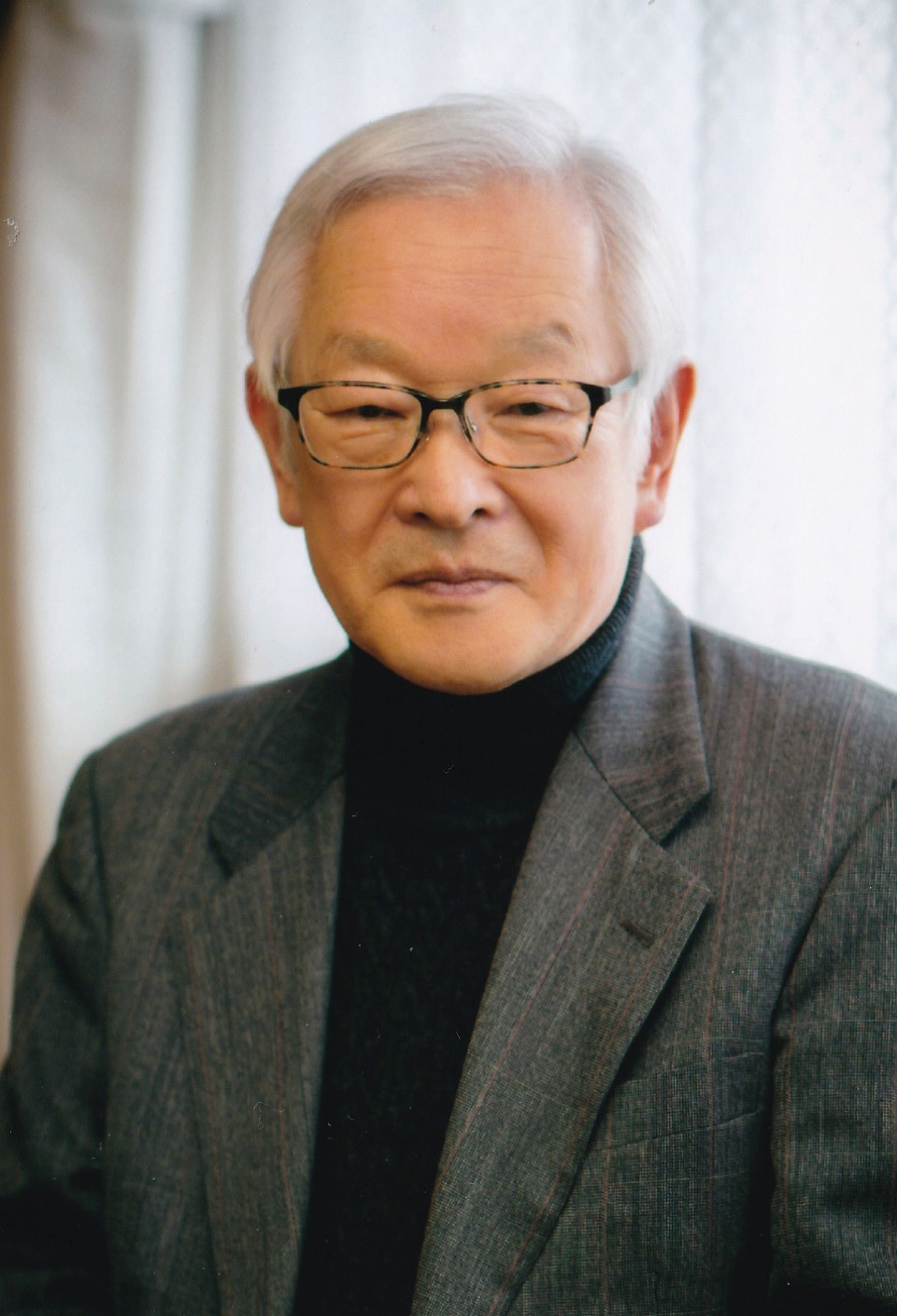残席状況の見方
残席状況に表示される記号の見方は以下の通りです。
-
定員まで余裕があります
-
残席わずかです
-
満席です
空席はありませんが、受講申込みボタンからキャンセル待ち登録を受け付けることができます。
-
残席未確定
そのままお手続きください。エラー画面が出た場合はお問合せください。
申込時には残席状況が変動している可能性があります。